照 明
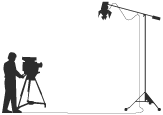
照 明
映像の美しさの半分は照明で決まるのだが、実際のVP収録現場で照明配置に多大な時間を掛ける事は、照明担当者がいない限り難しいのが現状ではないだろうか。そんな状況下でも最低限守りたい照明の基礎をおさえておこう。
一番大事なのは自然に見える事。一番最悪なのは、何でもかんでも明るくしようとして、バックに不自然な影を作ってしまう事だ。
Step-1~6を踏んで基本的な照明が出来るようになろう。
Step-1 照明の調整
照明の基本はライトを直接被写体に向けない事、必ずデュヒューザーを入れて光を和らげ、影の出方を常に意識することだ。
昨今はカメラの感度も上がり、よほどの暗い条件下でない限り、環境光を生かしてミックス光としてライトを配置すればな問題はないはずだ。
その時に使うライトとデュヒューザーの距離を変える事で、光の軟らかさを調整できる様にセッティングすればより柔軟な調整も可能となる。
Step-2 ロケ照明
野外を考えてみよう。
野外の撮影は花曇りがいい・・・とは言っても、そーうまくは行かないのがロケである。場所の融通がつけば極端な逆光は避けるなどするが、それでも少し補助光が必要な時にはレフ版を使う事になる。
レフ版をうまく使うには入射光と反射光の角度を考える事だ。
Step-3 光の質
ライトの光質について考えてみよう。
現代の室内照明の多くは蛍光灯だ。持ち込む照明器具はタングステン・照明用蛍光灯・LEDといったところだ。
室内蛍光灯に関しては、関東圏の50Hzではシャッタースピードを1/100にしてフリッカー対策をしておくとして、問題は安い蛍光灯の演色性の悪さだ。どうしてもグリーンの色が乗って発色が冴えない。
何故グリーなのかと言えば、人間の目は緑の光を一番明るく感じる特性があり、緑色の成分をたくさん出すように設計し、同じ電力でも明るく見せる事が出来るからだ。
同じ蛍光灯でも高演色蛍光灯(照明器具に使ってある)も販売されているが、ロケ先で蛍光灯を交換するのも現実的ではない。
持ち込む照明器具と併用して演色性を補正するのがベストだ。 ちなみに蛍光灯の色温度は4500K辺りだから、タングステン灯の3200Kの照明器具に、ライト用コンバーションフィルターB5かB6辺りを入れて、5500Kのデーライトととしてミックス光源としてホワイトバランスを取るのが実践的だ。
Step-4 基礎的なライトポジション
平面上のライト・ポジション
センター・ライト---被写体の正面(実際にはカメラのすぐ横)からの照明
プレーン・ライト---被写体のななめ前方45度付近からの照明
サイド・ライト ---被写体の真横、ビューラインに対して90度付近からの照明
リム・ライト ---被写体の斜め後方45度付近からの照明
バック・ライト ---被写体の真後ろ、ビューラインの延長線上からのライト
高さのライト・ポジション
プレーン・ライト---被写体の斜め上方からの照明
トップ・ライト ---被写体の真上からの照明
アイ・レベル ---被写体と同じ高さ、ビューラインと平行な照明
アンダー・ライト---写体の斜め下方からの照明
リア・ライト ---被写体の背後からの照明
各ライトの強さのバランス(照度比)
キーライト1(基準)・ フィルライト 1/3~1/2 ・ バックライト 1/2~1超
Step-5 暗部をつくる
これは、明るくするよりも難しく時間も掛かる。
レンブラントを引き合いに出すこともないのだが、「光と影の魔術師」と言われたレンブラントは、陰影表現の先駆者として照明技法の中で唯一、人の名前が付いた技法だ。
ライトポジションや特徴的な陰影で語られることも多いが、彼の絵画を観ると照明位置の問題ではなく、明暗が語る醍醐味にあるように思える。映し出された対象を雄弁に語るために闇を作る。CMやドラマ以外では使い難い照明かもしれないが、明るくする事ばかりが照明ではないことを肝に命じるために覚えておきたい照明技法だ。
Step-6 照明の注意事項
ロケ先のコンセント位置と電源容量の確認をすること。
電球破損に備えて予備を持つこと。
高熱を発する光源もあるので取り扱いには注意し軍手等を用意すること。昨今では蛍光灯やLEDなどの普及で電気容量と発熱の心配も少なくなってはいる。
a:2964 t:1 y:0
