台本を作る
台本・脚本・シナリオ・(ナレーション原稿)
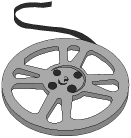
さて、具体的な作業に入ろう。
打ち合せも済ました。目的も確認した。撮影対象も決まった。
後は演出をどーするかって事になる。実際どーにでもなるのだが、ここから社会的制約と睨めっこすることになるのが普通で、先ずは予算、スタッフ数、〆切期間など、枠が決められる。 潤沢な資金と
〆切期日の無い制作なんてありえないのが現実で、少ない予算とスタッフ、
その上、短期の期日しかない状況で、どーするか?
選択の一つは・・・、「潔く断る」正論である。が、内部スタッフではそれも出来ない。そんな限られた状況の中で制作を強いられる貴方に一つの妙案を示そう。
それはナレーション原稿を先に作ること。前項でも台本の大切さを再三にわたりふれて来たが、このナレーションを入れる演出は、最も容易く短期間で効果的な表現ができる演出方法だと思う。例えば展示ブースの映像・企業ガイダンス・商品の取り扱い説明、全てナレーションを必要とする制作が多いジャンルで、応用範囲が広い演出方法だ。 業務としての制作の多くは、状況音を生かしつつナレーションがその上にかぶる演出が多い。
多くの業務制作の趣旨は、目的を如何に伝えるかに集約される。具体的内容になれば尚更説明が必要となり、ナレーションで語ってしまうのが手っ取り早くて効果的なわけだ。喋りには他に台詞・独白・インタビューなどの要素を取り混ぜて構成して行けばいい。
逆に短編でナレーションの必要の無い制作はどうするか。趣旨を具体的にすることに変わりはないが、次に全体のトーンを決めて流れをデザインして行くことだ。
色調、カメラの動き、音、ロゴの出し方、全てをコントロールする。
素材をデザインする感覚だろうか。ノンリニア編集環境はこの手の制作には強い味方といえる。

ノンリニア編集に関しては別項に譲るとして、ナレーション優先の作業ポイントを紹介していこう。
ナレーション優先で制作を進めると言う事は、読みのテキスト原稿が先ず出来上がっている事が第一条件となる。 ナレーションを書く時点で流れの半部は決まってしまう。
またテキスト原稿は詳細確認が取りやすく、最終原稿を作るまでに依頼者の確認を受けておくことも必須だ。
原稿が出来たら次に、内容に添って大きくブロックに分け、それをシーンとカットに分解してゆく。文脈内容から大まかなシーンに区切り、その内容に添った素材対象を決め、語尾の区切りを考慮してカットの長さを決めてゆく。
この作業の中でインタビューを入れる必要があれば、その箇所の判断をし、前後のナレーションの変更も加えてゆく。
この作業で、各シーンの撮影(素材)対象とカットの長さを割り出してゆく。
ナレーションと対比してカットの長さを判断することができ、実際の撮影に於いては、ナレーションの長さを考慮して無駄なカットの撮影や、必要以上に長いカットの収録をすることが無くなる。
注意点として撮影時に状況音を常に収録しておくことだ。それはナレーションの無い箇所の音圧変化を吸収し、流れをスムーズにしてくれる。
もちろんナレーションの収録は撮影が終わった後にする。これは撮影現場での突発的な変更を余儀なく強いられた場合に備えて、ナレーションの最終変更を可能にするためだ。
撮影を終えた時点でナレーションの収録に入る。
画面とナレーションの兼ね合いが重要な制作では、従来どおりの収録になるのだが、多くの場合ナレーションの音声のみを収録し、選りすぐりの音声を選別してノンリニア編集ラインに配置して行く。編集方式がノンリニアになり、音と画像を自由に配置調整できる環境下では合理的な作業手順と言える。
ナレーション原稿は特殊用語のイントネーションは事前に確認しておくことや、ナレーターが読みやすい原稿に整え、ペーパーノイズの削減を考慮し、文節を考えて文字原稿を用意するなどの注意を払う。 音声の収録は全体の作業からすれば、時間的割合は少ない作業だが、仕上がりの善し悪しを大きく左右する項目だ。作品のクオリティーを上げたければ、先ず音声にこだわる事だ。
収録に立ち会う場合には、収録テーク数をメモしておくと音声編集時に役に立つ。
裏技だが、ナレーター自身がICレコーダーに音声を録音して、音声ファイルを転送する方法も現在は可能な時代となった。
a:2651 t:1 y:1
