映像制作の流れ-Ⅱ
映像制作の流れ-Ⅱ

敢て言えば、制作手順は事故防止のような物だと思えばいい。
結果として、作品の評価を下される立場の身としては、依頼者の要望に応えないといけないわけで、打ち合わせの甘さが原因で、後の修正が増えるのは避けたいし、試写後の大幅な変更は事故に等しい。その事故をおこさない為に、Step-1~4の打合わせ・脚本作成・撮影・編集と段取りを踏むことになるんだ。
この制作に関わる人員が増え、出演キャストのスケジュール管理も必要となると、映画制作に使われる香盤表と呼ばれるスケジュール管理表が必要になるかもしれない。ここで香盤表などと言う言葉を使うと、一般的に映画制作をイメージされる方もいるかもしれないが、映画制作のように制作担当が明確に別れる大掛かりな組織制作と、現代のデジタル機器を用いた少人数の制作は大きく違う。いや、違えることが出来る時代になったというべきかもしれないな。 もちろん既存組織制作の諸々もデジタル化され大きく変わっているのだが、制作スタイルが変わることはない。それが社会ってもんだ、時間が掛かるんだ、何かが変わるにはね。

でも、一番変わらないのは、人が考えるっていうこと。こればっかりは変えようがない。人と会い、話を重ね、イメージを出し合い、全体の構成を考えていく。構成とは組み立てることだ。それは玩具のブロックで遊ぶ子供と変わりはない。よく見れば子供でも無闇やたらにブロックを組み立てたりはしない。車を作るとか怪獣を作るとか、何らかのイメージを持って組み立てている。
映像制作の構成も、そのブロックが色々な素材に変わっただけだ。何か作りたいイメージを求めて素材を組み立てる作業に他ならない。これは制作の柱とも言える作業で、如何様にも姿を変える変幻自在のダイナミックな作業だ。
人物が台詞を吐けばドラマにもなり、人物の状況を克明に描けばドキュメンタリーにもなる。素材は人物だけではない。写真も音も風景もアクションも光も全てブロックのひとつの要素だ。 試しに小片の用紙に思い付く全ての項目を、一枚一項目で書き並べてみるといい。 出来上がりが見えて来ないか? 並べた項目を整え説明を付ければ絵コンテの様に見えなくもない。
本来の絵コンテはカメラワークなどを記した、制作スタッフの意思疎通を円滑にする為の物なのだが、制作環境によってかなり違いがある。特にアニメやCM関連の絵コンテは、仕上がりをよりイメージさせる物となっている。
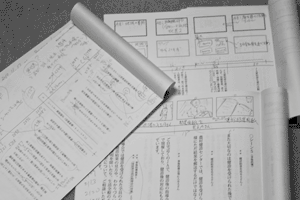
私の絵コンテなどは、脚本のシーンとカット分けした枠の下にナレーションを配置しただけの、秒数確認と、その日に進める作業進行メモを兼ねた一種のスケジュール管理表を兼ねたみたいなもんだ。
実際の運用では、当日の撮影カットに付箋を張り、撮影が済むたびにその付箋を織り込んで行く、そのための台帳みたいになっている。あえてカット割の細かな指示は書かない代わりに、撮影対象の見落としが無い様に要点項目を書く程度だ。 絵コンテ用紙への書き込みの多くは、編集時のファイル管理メモであったり、テロップ出しの位置確認であったり、CG及びエフェクト関連の細かな覚書などで絵コンテは汚れて行く。
制作スタッフが複数人となり、脚本(監督)と撮影・編集スタッフが別れれば、撮影カットのポジションから、カット割まで書き込む必要もあるだろうし、編集指示も必要になる。制作スタッフが増えれば増えるほど、制作意図をスタッフに的確に伝える道具として、絵コンテの重要度はまして行く。
老婆心ながら台本の大切さに再三ふれる事になるのだが、制作慣れしていない組織内で、スタッフが集められて事を進めると、身内の甘さから、取り合えず撮っておいてから考えようなどと、根拠の無い映像への期待のみで制作を始める事がある。
これは後々問題多発で余分な時間を取れれる事となるし、出来上がりも期待した程の作品が出来ずに終わってしまうことが多いので避けたい手順だ。
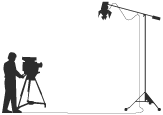
そうならない為にも余程の思惑が無い以上、間違っても撮影してから構成を考えるなどと思わない方がいい。用紙1枚でもいいから、趣旨と構成要素(何を撮るか)何を表したいか、期待することは何かなどを事前に書いてみるのは決して無駄にならない。
a:2881 t:1 y:0
